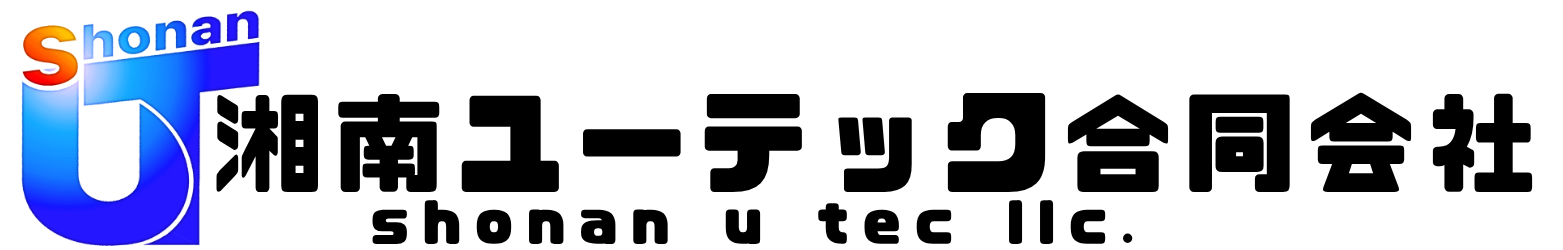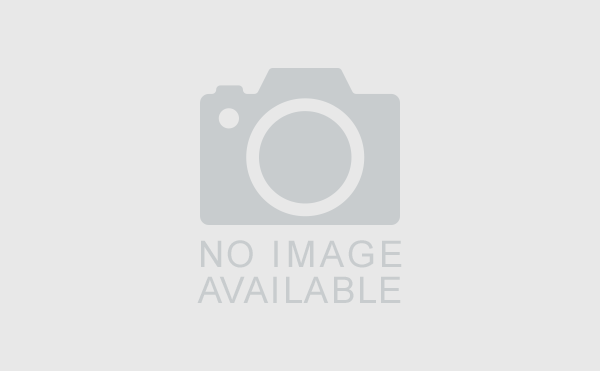斫り(はつり)の定番!切り付け作業の注意点!【意外に雑な職人が多い?】

こんにちは。
湘南ユーテック合同会社です✨
今回は建設・建築現場では欠かせない、斫り作業の一種【切付け作業】に対するマインドについて書いていきます。
斫り屋というと、コンプレッサーを積んだトラックで乗り付け、杭頭処理や大きなコンクリートを派手に壊す…そんなイメージを持たれがちです。
もちろん、それも斫り屋の大事な業務の一つです。
しかし、長い工期のマンション建設などにおいては、電動ピックを手に、延々とコンクリートの細かな躯体調整を行う時間の方が、実は圧倒的に多いのです。
左官屋さんなどの後工程が、スムーズに美しい仕上げをするために、不要な出っ張りをミリ単位で削り取っていく。
私たちは、日々、日常的に行われているこの一見地味で、しかし極めて重要な作業を「切付け」と呼びます。
この記事では、「大胆な斫りをガツガツと頑張っているのにイマイチ評価が上がらない」と感じている職人に向けて、
「切付け」という具体的な作業を通して、あなたの評価を高めるための考え方を解説します。
結論を言ってしまうと
- 雑な切付けになっていないか?
- スピードも大切だが初心に返って見直そう
- こまめな清掃と確認が大事
その意識を持つことであなたの職人としての価値が再評価されるかもしれません。
この記事を読んでほしい方
- 自分の仕事が正当に評価されていないと感じる
- 「スピード」か「丁寧さ」か、仕事の進め方に迷いがある
- 指示されたこと以上の価値を提供する方法を知りたい
- 現場で「指名される職人」になり、自身の価値を高めたい
・【切付けとは?】斫り作業の質を決める基本作業

「切付け」とは、一言で言えば、仕上げに向けて不要な部分を削り、整えるための繊細な斫り作業全般を指します。
具体的には、主に2つの場面でその真価が問われます。
- 新築マンションでの躯体調整:
コンクリートを打設した後、型枠のズレなどで生じた、本来あるべき姿からはみ出した部分を、図面通りに整形していく作業。 - 大斫り後の小口整形:
ブレーカーなどで大まかに躯体を壊した後、補修や仕上げに必要なレベルまで、断面をきれいに整える作業。
どちらも、次の工程を担う職人への「バトン」となる、極めて重要な作業です。
※これは一部の例であり、様々な斫り工事のまとめの小斫りに切り付けと言う言葉が使われることがあります。
なぜ「切付け」の質が評価に直結するのか
私自身、昔は「これで十分だろう」と思って作業した場所を、何度も呼び戻されてやり直した経験があります。
呼び出されるたびに、悔しさや情けなさを感じましたが、それと同時に「自分では気づけなかった残し」が必ずあることも学びました。
当時は若くて作業が雑だったとは言え、指摘してもらえたおかげで作業の質を意識できるようになりました。
現場には「速さに自信がある人ほど細かい残しに気づきにくい」という傾向もあります。
☝️あくまでも主観であり、速さとクオリティの両立ができている人も当然いらっしゃる、という前提です。
もちろん速さは武器ですが、それだけに集中すると、知らないうちに後工程へ負担を残してしまうのです。
そして、語弊を恐れずに言えば、自身の雑さに気づかないままのベテラン職人が多いのも事実であり、
逆に言えば当たり前の作業を丁寧にこなせる職人ほど現場での評価も上がり、結果的に会社からの評価につながるのです。
・そのハツリ、雑になってない?「良い切付け」と「悪い切付け」の決定的違い
✅ 良い切付けとは
結論はシンプルです。
下地補修の躯体調整の例で言えば
「左官屋さんが、何も言わずにそのまま補修作業に入れる状態」
これに尽きます。

(壁の下部切付け例 深掘りせずに適度に塗りしろがある )
邪魔な出っ張りが一切なく、かといって深くえぐり過ぎて余分な材料を使わせることもない。
後工程への、最高の思いやりが詰まった仕事です。
❌ 悪い切付けとは
これもシンプルです。
「左官屋さんが、あなたの後処理から始めなければならない状態」
斫り残しや忘れが点在し、結局左官屋さんが自分で手直しをする羽目になる。
あるいは、補修のことを考えずに深く斫りすぎて、無駄に材料を使わせてしまう。
これらは、後工程の職人の時間とコストを奪う、残念な仕事です。

(良くない切付け例 下部が斫り切れておらず、壁がまっすぐ降りない)
下部が出っ張っているから斫ったにもかかわらず、切付けが甘く結果的にハツる前と隙間が変わらない。
これではどんなに速くても意味がないですね。
極論、残した【ダメ】によって後工程が進めないようなら、それはやっていないのと変わりません。
基本的には、手をつけたのならしっかり決めていきたいですね💡
※実際はこの程度なら左官補修できる!とかそう言う話ではありません。
・なぜ雑な斫りになるのか?「速い職人」が陥る、無自覚の罠
速いだけの斫り屋になるな
以前【左官屋との関係】の記事でも書いたのですが、
【速ければ良い】と言うものではなく、かと言って【丁寧であれば時間がかかっていてもいい】と言うわけでもない。
どっちなんだい!!!(某きんに君)
極端にどちらと言うものではなくバランスが大事です!
その上であえて言うならば、まずは確実に後工程に渡せる仕事をすることが大切です。
雑な切り付けに本人は気付いていない事実
では、なぜ「適当な切付け」になってしまうのか。
それは、多くの場合、やっている本人に悪気もなく【雑だという自覚】すらないからです。
特に、「仕事の速さ」に自信がある職人ほど、この罠に陥りやすい傾向があります。
例えばこのような負の連鎖👇
作業を進めることに夢中になり、各所に少しずつダメ(やり残し)を残していることに気づかない。
↓
とりあえず形になっているので、監督や左官屋さんもその場では「速いね!」と褒めてくれる。
↓
本人は「自分の仕事は速くて質も良い」と勘違いする。
↓
後日、仕上げに入った左官屋さんが、点在する手直し箇所に気づくが、今さら本人を呼び戻すのも面倒なので、自分で直してしまう。
↓
結果、雑な仕事をした本人は、自分の仕事が雑だったと知る機会を永久に失う。
↓
現場や職人間では「あの人、仕事は早いんだけど雑なんだよね」とイメージが定着。
これが、現場で起きている「不都合な真実」です。
職人が減っている今、「あいつは仕事が雑だ」と正直にクレームを入れること自体がはばかられる空気感も、この問題に拍車をかけています。
一生懸命頑張っている職人ほど、無駄とまでは言いませんが、こんなに勿体無いことは無いですよね。
・「たかが切付け」その認識が、あなたの評価に直結する
「切付け」は、斫り屋にとって当たり前すぎて、つい適当になりがちな作業です。
しかし、その「たかが」という意識が、あなたの評価を静かに、しかし確実に下げています。
あなたの作業のすぐ後に入る左官屋さんが、あなたの仕事を見てどう感じるかを意識しましょう。
左官屋さんにとっての良い斫りをしているその評判は、必ず監督の耳に入ります。
そして監督は、あなたの会社にこう伝えるのです。
「次のも、あの人でお願いします」と。
会社の上司は、あなたの日常の作業を直接見る機会はほとんどありません。
だからこそ、現場からの「指名」という客観的な評価こそが、会社でのあなたの価値を決定づける、最も強力な武器になるのです。
・こまめな清掃や確認でダメ残しを断ち切る習慣
こまめな確認を怠るな
では、どうすればこの無自覚の罠から抜け出せるのか。速さばかりを追ってきたあなたも、これから丁寧な仕事を覚えたいあなたも、意識すべきことはたった一つです。
一度に広げ過ぎない「こまめな清掃と確認」を、作業のルーティンに組み込む。

👇これは、あなたを馬鹿にしているわけではありません。
もともと、あなたも一つ一つの作業を丁寧に覚えて行ったのかもしれません。
しかし、後期に追われ、現場に貢献しようと頑張りスピードを求めた結果、
知らず知らずのうちに仕事の質を落としている可能性があるのです。
💡切り付けの質を見直す為に。
- 掃除のタイミングを早める:
作業を広げすぎる前に都度掃除をし、斫り残しがないか自分の目で確認する。 - 垂直・水平を確認する:
壁の切付けなら、本当に垂直に収まっているか。
開口部なら、カッターラインをはみ出していないか。
自分の仕事を過信せず、初心に帰って確認する。
あなたの仕事が速いことは、もうみんなが知っています。
「あの人はスピードだけはあるんだけどなぁ…」と陰で言われないために、
ほんの少しだけ、この「こまめな確認」を意識するだけで、あなたの評価は劇的に変わるはずです。
💡斫り残しのある悪い例
急ぐあまり、広い範囲で斫り散らかして掃除を後回しにして、
終了間際にまとめて掃除。
☝️斫りガラが散乱しているため忘れやミスに気づきにくい。
☝️終わり間際に掃除するので、人によっては早く帰りたくて慌てて掃除するかもしれません。
☝️すると細かい斫り残しには気付きませんし、ギリギリの時間に気付いても手直しする余裕がありません。
もし、この記事や何かをきっかけに自身の作業を見直す機会があるのなら、
少しだけ初心に立ち帰り、現場や後工程に必要な斫りを意識すると改めて良い評価へと繋がるでしょう。
・やり残しが生む「見えないコスト」を意識する
たった一つの斫り残しが、後工程の作業を止めてしまう。
その時間的損失は、あなたが思っている以上に大きいのです。
やり直しのために、もう一度斫り屋さんを手配し、道具を運び、養生をして…場合によってはその間現場が止まるなんて最悪な事態も...
その全てが、現場にとっては多大なコストになります。
あなたの「こまめな確認」は、単に仕事を丁寧にするだけでなく、
現場全体の無駄なコストを削減しプロジェクトを円滑に進めるための、非常に価値のある貢献なのです。
・資格や特別教育の受講であなたの価値をさらに高める
切付けを丁寧に仕上げること自体が、すでに現場で信頼を得る最短ルートです。
ただし、少し話はそれますが、さらに「見える形」であなたの価値を高めたいなら、資格取得も大きな武器になります。
例えば、斫り作業には粉塵作業や振動工具の取り扱いに関する特別教育が必要です。
まだ受けていない方は、学科だけで取得できる比較的簡単なものもあるので、まずはここから挑戦してみるのがオススメです。
さらに大きくステップアップしたい方は、これまでの職人経験を活かして2級施工管理技士(建築または土木)などに挑戦するのも良いでしょう。
現場での信頼を「資格」という形に残すことで、仕事の幅も広がり、監督や会社からの評価も確実に上がります。
今では建設系の資格や特別教育もE-ラーニングで受講可能です。自宅や空き時間で学べるため、平日に現場を空けたり日曜を返上する負担も減りました。
代表的な講習先も紹介しておきます。
オンライン受講先
- SAT株式会社・・・日々の作業に必要な特別教育の受講や、国家資格に合格するためのオンライン講座で勉強もサポート!
☝️私が実際に特別教育を受けた受講先です。
(数ある受講先の中のいい例ですので、事業者様やご自身に合った受講先を選びましょう。)
資格はあくまで手段ですが、「切付けの質」と並んで、あなたの職人としての価値をさらに裏付けてくれるはずです。
まとめ:当たり前を当たり前以上にやる。それが職人の仕事。
- 切付けとは、仕上げに向けて不要な部分を整える繊細な斫り作業
- 良い切付け=後工程がそのまま作業に入れる状態
- 雑な切付けは「残し」に気づかない無自覚から生まれる
- こまめな確認をルーティン化することで質が上がる
- さらに価値を高めたいなら、資格取得や転職活動で“見える信頼”を手に入れる
切付け作業は、私たち斫り屋にとって当たり前の日常業務です。
しかし、その「当たり前」の質を、どこまで高められるか。
そこに、ただの作業員と、現場から本当に信頼されるプロとの、決定的な差が生まれます。
「切付け」の質を高める3つのマインド
- 後工程を思いやれ:あなたの仕事は、次の職人への「下地づくり」である。
- 自分を過信するな:「速さ」という武器に溺れず、こまめな確認を怠らない。
- 現場全体を見ろ:あなたの仕事一つが、現場全体のコストと評価に繋がっていることを意識する。
この記事が、あなたの明日の「切付け」を、少しだけ変えるきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。