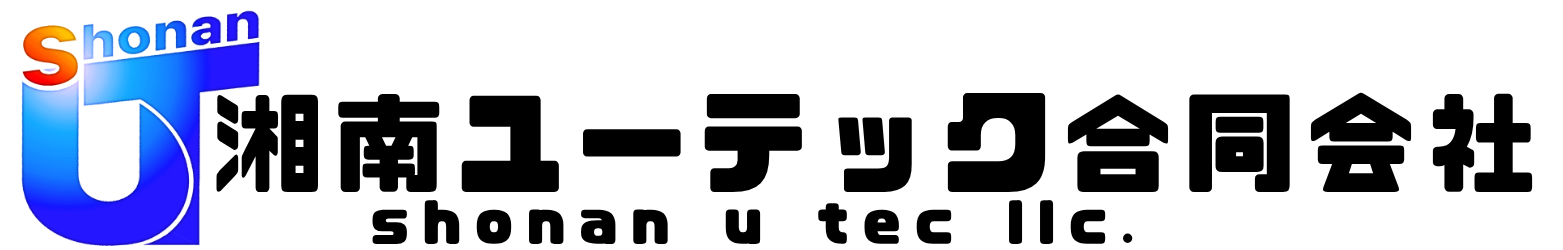斫り(はつり)職人に必要な資格は?受講するべき特別教育一覧とオンライン受講のススメ

こんにちは!湘南ユーテックです!
今回は斫りや解体作業を行うにあたり、数ある資格関連の中で、オンラインでも受講出来る【特別教育】に重点を置き解説していきます。
「資格なんてなくても、腕さえあれば食っていける」
昔の現場には、そんな気骨のある職人がたくさんいました。
今でも「ウチの会社は大丈夫」「自分は経験豊富だから関係ない」と思っている職人さんもいらっしゃるかもしれません。
しかし今や、安全のためのコンプライアンス(法令遵守)が強化され、危険の認識を厳しく問われる現場作業では、
「知らなかった」では済まされない資格や特別教育が数多く存在します。

この作業するのにそんな資格必要だったかな?
数年前は普通に作業してたけど・・・。

下請け業務がメインだったり個人事業の様な会社では、
自分からリサーチしないと新しいルールや必要資格の新情報って
入ってこなかったりするんですよね。
💡この記事では、日々の斫り・解体作業に、実はどのような特別教育が必要なのか。
そして、「忙しくて講習のために現場を空けられない!」と感じている多忙な職人や事業者のために、
仕事を休まずにそれらを取得できる現代的な方法【オンライン受講】について解説します。
💡実際に私がオンラインで特別教育を受けた受講先はこちら👇
事業者様から実際によく聞く
「あの現場は資格証にうるさいから、人を選ばないと手配できない」
「お金の問題じゃないけど、講習に行かせる暇が無い」
この記事が、☝️そんな悩みを解消する一つの手がかりになるかもしれません。
この記事を読んでほしい方
- 日々の作業に必要な資格を正確に把握していない職人の方
- 「今さら…」と思っているが、本当は資格について気になっているベテラン職人の方
- 従業員に効率よく資格を取得させたいと考えている事業者・経営者の方
- これから斫り業界を目指す、向上心のある若手・未経験者の方
① 「特別教育」とその他資格との違い
まず、大前提として理解しておくべきことがあります。
これから紹介する特別教育は、会社や現場が勝手に決めたルールではありません。
これらは全て、過去に起きた数多くの労働災害の教訓に基づき、
労働安全衛生法という国の法律によって、事業者に実施が義務付けられているものです。
「これを持っていないと、その作業をした瞬間に法令違反の対象になる」という重要なものになります。
現場によっては協力会社への信頼のもと資格証の確認が甘いこともありますが、
規制の厳しい現場でなくとも、あなた自身の安全のために対象の作業を行う上で受講は絶対に必要です。
☝️「資格」と構えず、まずは「特別教育」から始めよう
「資格」というと、分厚いテキストで勉強して、難しい試験に合格して…と、少し億劫に感じてしまいますよね。
ご安心ください。日々の斫り作業に、いきなりそこまでのレベルは求められません。
まず私たちが身につけるべきは、安全に日々の作業を行うための「安全衛生特別教育」です。
これは、特定の危険な作業を行うための【許可証】のようなものだと考えてください。
私たち建設作業員が大まかに通称【資格】と呼んでいるものは以下の図のように分けられています。
斫り職人の資格キャリアパス(例)
コンクリート造工作物解体等作業主任者)

なるほど、資格にも階層があるのは分かったけど…
結局、「特別教育」と「技能講習」って、具体的に何が違うんですか?

良い質問ですね!現場では全部まとめて「資格証」なんて呼んだりしますが、この二つには明確な違いがあるんです。そこを理解することが、賢いキャリアプランを立てる第一歩になりますよ。
✅ 特別教育は、その作業を行うための「許可証」
特別教育は、国家資格や免許とは少し違います。
これは、労働安全衛生法で定められた【特定の危険な作業を安全に行うための、最低限必要な知識と技術の教育】です。
対象の作業に就くための“許可証”のようなものだと考えてください。
会社(事業者)が、従業員に必ず受けさせなければならない「義務教育」でもあります。
✅ 技能講習は、より高度な作業のための「技能資格」
一方、技能講習は、特別教育よりも【危険度が高い、特定の作業】を行うための、より高度な教育です。
学科だけでなく実技もあり、最後に修了試験に合格して初めて修了証がもらえます。
その資格はあなた個人の価値を見出す「武器」として、一生使い続けることができるのです。
基本的に、技術者としてスキルアップを目指すなら技能講習までで十分でしょう。
✅キャリアアップを目指すなら上位資格にチャレンジ!
リーダーとして上を目指したい、会社の運営や現場管理に関わるのであれば管理系の資格の取得にチャレンジしましょう。
合格すれば今後のキャリアを形成する上で更に大きな武器になります。
次に斫り・解体職人に最低限求められる特別教育を順に見ていきましょう。
② 斫り・解体作業に必要な特別教育一覧

・振動工具取扱いに関する特別教育
電動ハンマーや削岩機といった振動工具は、私たちの商売道具であると同時に、身体を蝕むリスクも孕んでいます。
長期間使用すると、指先が真っ白になり感覚を失う白ろう病や筋肉や骨に異常をもたらす振動障害を発症する可能性があり、一度発症すると完治は困難です。
この教育は、そのリスクからあなたの職人生命を守るために必要な知識を学ぶためのものです。
振動工具を取り扱う上で必要な保護具や対策の知識をつけて、稼ぐための資本であるあなたの身体を振動被曝から守りましょう。
・粉じん作業に関する特別教育
コンクリートを斫れば、粉じんは必ず発生します。
これを長期間吸い続けることで発症する「じん肺」は、気づいた時には手遅れになっていることが多い静かなる脅威です。
正しい知識と対策を学ぶことは、自分自身の健康を守るための最低限の義務と言えます。
斫り作業時に発生する粉塵は、セメントなど多く吸い込むと有害な物質が含まれています。
古い建物の斫りや解体ともなると微細なアスベストなどの物質も知らずに吸い込むことになりかねません。
長期的に見て肺癌になるリスクも増加していきます。
若いうちから不快な粉塵に慣れてしまわないように、適切な知識を身につけ、必要な保護具で対策しましょう。
・自由研削用といしの取替え等の業務に係る特別教育
ディスクグラインダー(サンダー)やカッターの砥石(ブレード)交換は、日々の作業の中で当たり前にやっていることですが、
実は法律でこの教育の受講が義務付けられています。
なぜなら、不適切な取付けにより破損した砥石の破片が凶器となり飛び散るなど、極めて危険な事故につながるからです。
自分だけでなく、周りの仲間を危険に晒さないためにも必須の項目です。
実態として、グラインダーそのものを使用するのに資格は必要ありません。
しかし、斫り・解体作業員として長期でグラインダーを使用する上で砥石・ブレードを交換する機会は必ずあります。
その交換することに対して特別教育が必要になります。
・フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
高所作業は、建設業の労働災害で最も多い墜落・落下事故のリスクと常に隣り合わせ。
2019年以降はフルハーネス型が原則必須となっており、これはあなたの命を守る命綱です。
作業床の高さによって同ベルト型とフルハーネス型を使い分ける必要があったりなど、
適切な使い方を学ぶためにも足場に登る可能性のある作業者は必ず必要とする資格の一つです。
内部外部問わず高所作業がある可能性がある労働者は実質必須となる特別教育ですね。
どうせ受けるのであれば改めて高所作業の危険性や対策について再認識したいところです。
・足場の組立て等の業務に係る特別教育
「自分は足場を組まないから関係ない」というのは大きな誤解です。
特別教育は組立・解体作業者に義務付けられていますが、実際の現場では斫りや塗装など、足場上で作業する職人が一時的に足場板を外したり、
壁つなぎを外したりすることもあります。
そうした行為は「足場の変更」に該当するため、特別教育が必要になります。
・酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育
地下ピットやマンホール内など、密閉された空間で作業する際に酸欠事故を防ぐために必要です。
自分は大丈夫と思っても、気づかないうちに意識を失うのが酸欠の本当の怖さです。
長期密閉された空間だと、硫化水素が蓄積している可能性もあり、吸い込めば大変危険な重大事故につながります。
構内やピット内での斫り・解体作業も多くあるので、事前に特別教育を受講して適切な換気や濃度測定の知識を身につけましょう。
③ 特別教育は「オンライン受講」で仕事を休まずに取得!
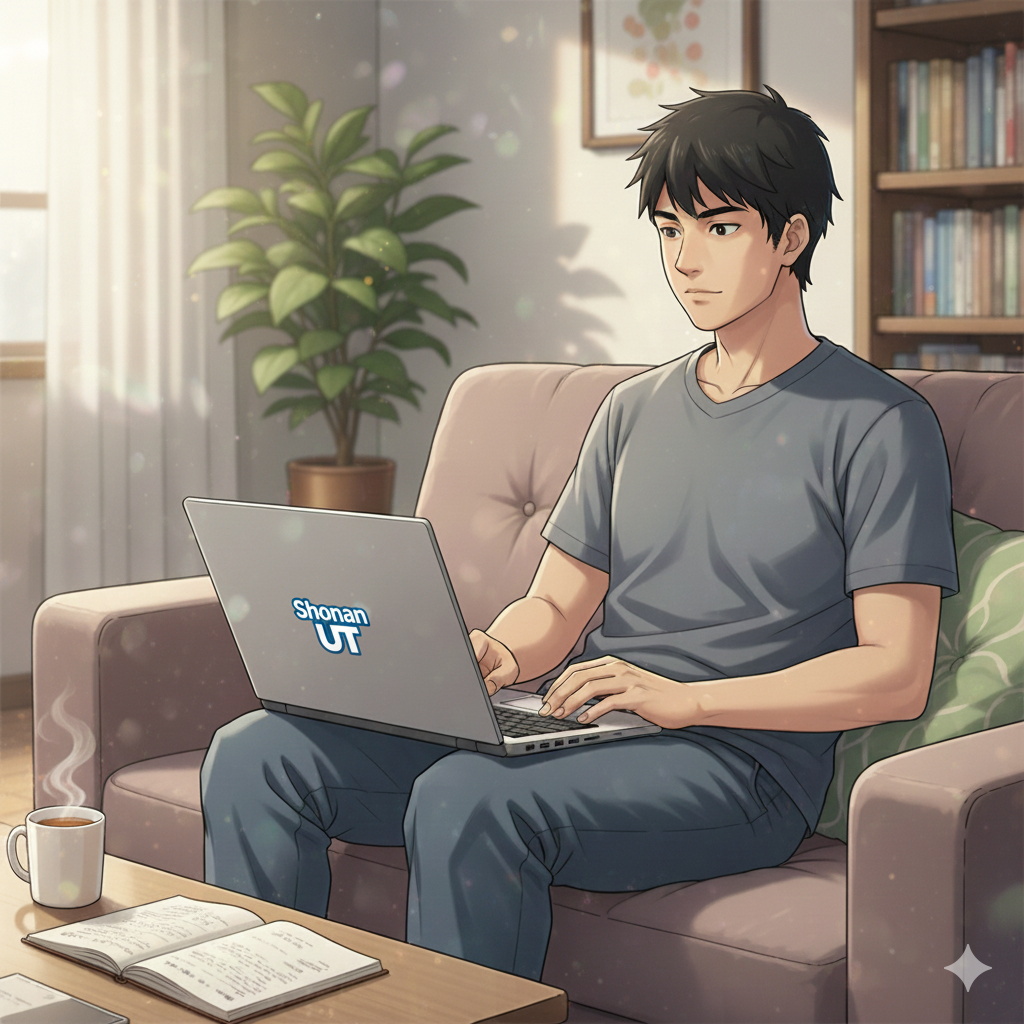
・「必要なのは分かっているけど、講習のために現場を休めない…」
職人なら誰しもが、そして従業員を抱える事業者なら尚更にそう思いますよね。
しかし、その悩みはもはや過去のものです。現在、多くの特別教育がオンライン(Eラーニング)で受講可能になっています。
✅ 職人にも、会社にもメリットは大きい
- 職人のメリット:
現場を休まずに済む。つまり給料が減らない。
往復の交通費も時間もかからない。
自分のペースで、スマホ一つで学習できる。
休日の空いた時間にリラックスして受講できる。 - 事業者のメリット:
従業員を現場から離脱させずに済む。
つまり会社の売上を止めずに、従業員のスキルアップと法令遵守を両立できる。
これにより「資格者がいないから、あの現場は受けられない」という機会損失も防げます。
もちろん、個人でなく会社都合で受講させるのであれば、時間外や残業として手当をつけるなどの配慮が必要です。
✅ まずはここから!オンライン受講だけで取れる学科のみの特別教育
特に、以下の特別教育は学科(座学)のみで完結するため、オンラインとの相性が抜群です。
動画視聴とテストだけで、後日、自宅や会社に修了証が届きます。
まずはこれらをオンラインで必要順に取得するのが、最も効率的な戦略と言えるでしょう。
- 石綿取扱い作業従事者特別教育(内装解体では必須!)
- 粉じん作業特別教育
- 振動工具取扱い特別教育
- 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育
- 足場の組立等作業従事者
※受講先によっては模擬的に実技を行う場合もあるので各受講先に従ってください。
✅オンライン学科+事業所での実技が求められる特別教育
一方で、以下の特別教育は、学科に加えて実技の時間が法律で定められています。
- 自由研削用といしの取替え等の業務に係る特別教育
- フルハーネス型墜落制止用器具 他
これらの教育も、学科部分はオンラインで済ませることが可能です。
問題は実技ですが、オンライン講座では、あなたの会社や事業所で十分な知識と経験を持つ者
(有資格者や経験豊富な先輩職人)が指導役となり、
法令で定められた時間の実技教育を行い、その記録を提出するという方式が認められています。
事業者の責任のもと、適切な指導者が実技を行い、指導者名を記入をする必要があります。
一人親方の場合も、協力会社の有資格者などにお願いして受講することが可能です。
学科だけでは修了扱いにならない点だけは、注意してください。
※玉掛け作業の資格は?
私たちの作業で斫りガラや廃材の搬出で使う玉掛けをなぜ必要な特別教育に入れていないかと言うと、
特別教育の受講で得られる玉掛け作業の資格が1t未満のクレーンなどに限られます。
実際に現場でフレコンに詰めたガラや廃材を下ろす際に使うのは常設のクレーンであったり、
数十トンクラスのラフターがほとんどです。
絶対にユニック規模の玉掛けしかしないのであれば特別教育でも良いのですが、
おそらく後々足りなくなる可能性があるのであれば、最初から技能講習で1以上の資格を得た方が良いでしょう。
他にも、特別教育と技能講習で似た項目の項目がありますが、
作業に従事する上で扱える範囲が違うので必要な範囲を確認して受講しましょう。
💡実際に私がオンラインで特別教育を受けた受講先はこちら👇
④ オンライン受講可能なキャリアアップのための教育
作業に必須の特別教育をクリアしたら、次はあなたの「市場価値」を上げるための、より強力な武器です。
これらの資格は、職長へのステップアップや、より条件の良い現場を目指す上で非常に有効です。
職長・安全衛生責任者教育
チームをまとめる職長・リーダーを目指すなら必須。
元請けや大手ゼネコンの現場では、これが無いと話にならないケースも多いです。
「ただの作業員」から「現場を管理する側」への第一歩です。
保護具着用管理責任者教育
2024年4月から新たに義務化された比較的新しい教育です。ここで一つ、非常に重要な注意点があります。
日頃から他業種よりも保護具の着用を重要視している斫り屋だからこそ、
この教育の名称から【誤解したまま従業員に受講させるケース】も少なくありません。
今後必要になる資格の一つではありますが、必要性を理解した上で受講を進めましょう。
【注意】この資格は「全ての保護具」の管理者ではありません。
私も誤解していました。
この名称から、斫りに必要な「防じんマスクや防振手袋、安全帯などの管理者かな?」と思われがちですが、法律上の対象は主に「化学物質のリスク」から作業者を守るための保護具(防毒マスクなど)に限定されています。では、なぜ私たち斫り屋に関係があるのか?
それは、コンクリートの「粉じん(結晶質シリカなど)」が、法律上【化学物質】として扱われるケースがあるからです。
この資格は、「化学物質管理者」というさらに上位の管理者が行ったリスクアセスメントで
「この作業で発生する粉じんは有害だ」という判断に基づき、現場で実際に保護具を選定し着用を管理する役割を担います。
今後、元請けから「粉じん対策として、保護具着用管理責任者を選任してください」と求められる現場が増えていく可能性はあります。
職長や事業者がこの資格を持っておくことは、会社の安全管理体制をアピールし、受注機会を増やすための、強力な武器になるでしょう。
しかし現時点で制定ルール上では【保護具着用管理責任者教育】単体で機能するものではなく、
【化学物質管理者】との抱き合わせで初めて機能する資格であることを理解しておきましょう。
⑤ まとめ:資格はあなたの価値を高める資産になる
ここまで、斫り職人に求められる資格について、現場目線で解説してきました。
適切な資格を持つことは、監督や元請けからの「信頼」に繋がり、ひいては会社内での評価を高めます。
もちろん、どんな資格も持つなら多いに越したことはないですが、
使いもしない資格取得に時間ばかり使っていては【ただの資格コレクター】になってしまいます。
あなたが建設業に携わる職人さんであるならば、まずはこの記事で紹介したような、
日々の作業に直結する資格から優先的に計画を立てていくのが賢明です。
勤めている会社に積極的に相談するのも良いでしょう。
仕事に対する前向きな姿勢を評価してもらえたり、受講する上での費用や手当の相談に繋がるかもしれません。
明日からできる行動ステップ
- まず自分の作業に必要な資格や教育を確認する:「法律で義務」の特別教育に漏れはないか?
- オンライン講座を調べる:学科のみの資格から、効率的に取得計画を立てる。
- 実技指導の体制を整える:実技が必要な資格について、社内や協力会社に指導を依頼できるか確認する。
- 将来を見据えキャリアアップ資格を検討する:職長を目指すのか?専門性を高めるのか?
最後に。
今回はオンラインで取得しやすい特別教育に焦点を当てて解説しましたが、
個人で職人としてのキャリアアップを狙う方も、
会社・企業単位で従業員のスキルの底上げをしたい経営者様も、
隙間時間を使ってできる受講を考えてみてはいかがでしょうか。
弊社自身、オンライン受講やE-ラーニングによる建設業関係の資格取得についてはつい最近まで知りませんでした。
まだまだ、【特別教育の受講=平日の作業を空けて講習会で受講】の認識だけの方も多いと思います。
同じ教育時間だとしても、空いた時間を有効に使える選択肢を考えてみてはいかがでしょうか。