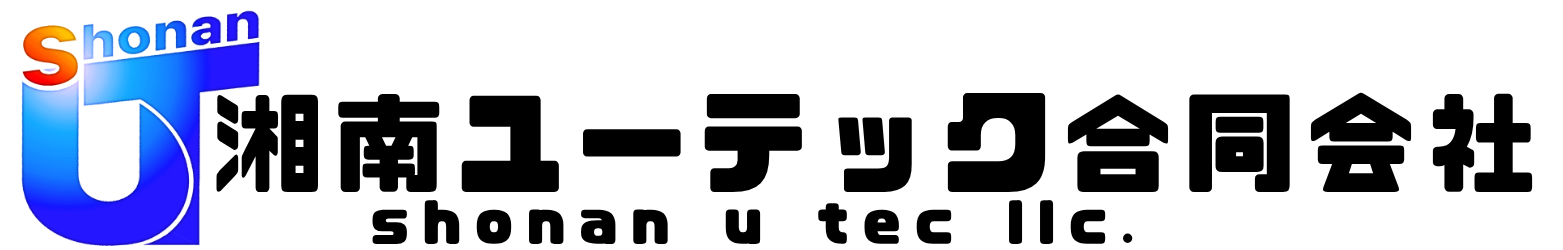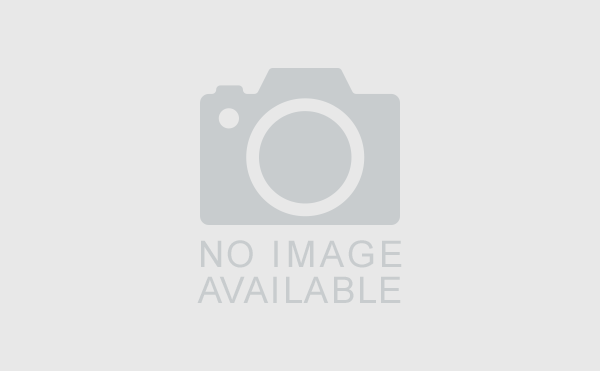【斫り屋が解説】現場の熱中症対策義務化ガイド|事業者・一人親方の備え
〜小規模事業者・協力会社でも責任あり!教育・グッズ・ウェアラブルまで網羅〜
🔍 はじめに
皆様、暑い中での日々の作業本当にお疲れ様です。
特に私たち斫り(はつり)・解体業者は、防塵マスクや保護メガネの着用が必須なため、熱がこもりやすく、その厳しさは身をもって感じています。
今回は、熱中症対策の義務化についてです。
私たちのような小規模企業や、職人兼社長として事業を営んでおられる方々、
日々の現場作業に追われていると、ルールの改正や義務化といった情報は、なかなか耳に入ってこないものです。
現場の休憩時に他の方から聞いたりして、自分から調べて初めて詳細を知るなんてことも多いです。
まだまだ多い『え!?義務なの!?罰則は??』と気になった方に向けてまとめた記事になります。
- 令和7年(2025年)6月1日に、熱中症対策が罰則付きで正式に義務化されました 。
- 対象は、WBGT28℃以上または気温31℃以上の環境で、継続1時間以上または1日4時間以上の作業 。
- 違反すると事業者単位で6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金があり、すべての事業者(法人・個人問わず)が対象 。
👉すべての事業者が対象と言うところがポイントです。
「自社が元請けでないから関係ない」は通用せず、「協力会社や一人親方でも教育・環境配慮は自社の義務」です。
一人でも社員・従業員を雇っていれば対策・教育・周知の義務が課せられますので注意しましょう
1. 義務化の背景と理由
- 日本の気候変化に伴い、労働現場における熱中症による重篤な事例や死亡事故が増加。
- 調査では、熱中症災害の90%以上が「初期対応の遅れ」に起因したという実態。
- 労働安全衛生法のこれまでの指針では、暑熱対策は“努力義務”にとどまっていたことから、重大な安全義務として「見える化」されました。
災害級の暑さと言われていた気温が、近年では常態化してきました。
夏を待たずにやってくる猛暑日、毎年『早く来る夏』に疲れた頃にくる7月以降の夏本番。
頭では慣れたつもりで作業していても、身体が付いていかずに熱中症で倒れる…。
『自分は大丈夫』『まだ頑張れる』と仕事熱心な職人ほど無意識に無理しがちです。
「義務化」と聞くと、ルールで縛られるように感じますが、
半ば強制することにより個人単位での見えない無茶や気付かない無理を減らし、
全員が適切な対策を行いながら作業に臨む、そのような理想の実現に向けた対策の義務化だと感じます。
どうしても、体調の悪さを一番自覚できるのは自分自身なのに、仕事中に自発的に具合が悪いと進言できないものです。
まだ頑張れると続けた結果、取り返しのつかない重体になりかねません。
この義務化を機に、現場や事業者単位で対策し、自発的に体調不良を申告でき、周りも気づけるような環境づくりをして、
今まで以上に仲間の顔を意識して予防していきましょう。
2. 対象者は誰?どんな現場?
対策義務・罰則の対象は?現場単位?会社単位?
熱中症対策義務の実施主体は、基本的には「事業者」です。
つまり、作業員を雇用・派遣している法人・個人事業主が対象になります。
主に対象となる現場環境の例
- 建設現場(とび・土工、解体、内装、設備工など)
- 工場(高温多湿な製造ライン)
- 運送業(倉庫や積み下ろし作業場など)
- 農作業(ビニールハウスなど)
- 屋外イベントや設備保守など
- もちろん、私たち斫り屋・解体屋も対象です。
※短期バイトや一人親方でも「他人を雇っていれば」対象になります。
🌟ただし、実際の現場(作業所)では、現場管理者(元請)が対策を統括するケースも多いため、以下のような整理が必要です。
事業者としての義務(協力会社・職人の所属会社など)
- 所属する作業員への熱中症リスクの説明と教育
- 被災者発見時の処置や報告の手順化と周知
- 必要な対策用品の支給・指導
- 労働時間・休憩環境の見直し指導
実際の現場管理者としての義務(元請・ゼネコンなど)
- WBGT(暑さ指数)計の設置
- 日陰や休憩所の整備
- 全体ルール(こまめな水分補給の時間設定など)の実施
🔎 POINT:自社で現場を持っていなくても、「労働者を出している以上、事業者としての責任が問われる」構造になっています。
義務の対象は
①自社で労働者を使役している全ての事業者と、
②作業環境がWBGT28℃以上または気温31℃以上—かつ連続1時間以上および一日4時間以上の作業を行う作業所です 。
【注意】協力会社であっても「知らなかった」では済まされない
現場の管理は元請が主導することが多くても、協力会社・下請会社も「自社の職人に教育・装備を用意する責任」があります。
特に個人事業主や一人親方など、作業員を雇用せずとも「請負」や「協力契約」で作業する場合も注意。
労働安全衛生法上の解釈によっては、同様に安全配慮義務が問われるケースもあります。
例えゼネコン現場への協力会社であっても適用され、教育・備品・応急対応などは自社で準備する必要があります。
3. 義務化された「3つの柱」
厚生労働省が示している、事業者が現場で講じるべき主な義務は、大きく分けて以下の3つです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ① 体制整備(見つける) | 「自分または周りが異変を感じたら報告」の体制を作り、現場ごとに連絡先や手段を周知。 |
| ② 手順作成(判断する) | 作業中断・冷却措置・医療機関受診・搬送体制など、対応フローを文書化し、周知。 |
| ③ 周知・教育(対処する) | 上記内容の周知とともに熱中症の基礎知識や対策について各事業所で教育を行い記録を残す。 |
4. 教育内容を具体的に整理
教育義務の内容は明確です。以下のようにマニュアル化しましょう:
- 熱中症とは何か?(原因と症状)
- 軽症vs重症の見分け方と対応
- WBGTの理解(28℃で厳重警戒、31℃で運動原則中止など)
- 水分・塩分補給の方法(500 ml/時+塩飴・タブレットなど)
- 冷却方法と休憩設計(首筋・脇・脚付け根への冷却)
- セルフチェックの声かけルール
- 報告→対応→搬送の実務フロー(119番通報、#7119の活用※など)
📘 教育手段:朝礼の説明、資料配布、動画視聴、e‑ラーニング、記録簿やサイン台帳で実施記録を残しましょう。。
5. 各事業者が現場でできる具体的な熱中症対策例
- 熱中症対応マニュアルを用意し、朝礼で周知
- 自社でWBGT計を持参・測定し、記録をとる
- 体調確認をLINEなどで朝に報告してもらう
- こまめな水分・塩分補給(例:スポーツドリンク、塩飴など)
- ファン付き作業着+速乾インナー(最近では空調服の着用が義務付けられている現場もあります)
- 休憩所の涼しい環境づくりは重要(エアコンを効かせたハウス)
- 作業前のウォームアップ/ラジオ体操で体調を整える(作業前に体を動かして、暑さになれる為に効果的)
- 異変を感じたら即休憩報告→冷却(一人で勝手に休まずに、仲間への声掛けや助けを求めること)
- 1時間おきの休憩タイマーを設定する(『疲れていないから休憩しない』ではなく、水分補給のために必ず手を止める)
これらの対策を実践することは、命を守るだけでなく、安全衛生協議会などで評価され、信頼される事業者としてのアピールにもつながります。
6. 基本グッズ+最新ウェアラブルも紹介
常備したい基本グッズ
- ファン付き作業服(通称)空調服
- 塩分タブレット・塩飴
- 水筒
- 緊急用熱中症対策バッグ
緊急用 熱中症対策バッグおすすめの中身
【体を冷やす】〜とにかく体温を下げることが最優先〜
- 氷のう
- なぜ良いか?: 現場に製氷機がおいてあれば、氷を入れてすぐに冷却可能です。普段は小さくたたんでコンパクトになるので持ち運びにも便利。
- 瞬間冷却パック(叩けば冷えるタイプ)
- なぜ良いか?: 氷がない場所でも、叩くだけで一気に冷却できます。首の両脇、脇の下、足の付け根など、太い血管が通る場所を冷やすのに最適です。氷のうと並んで最重要アイテムです。複数個入れておきましょう。
- 冷却シート(熱さまシートなど)
- なぜ良いか?: 冷却効果は限定的ですが、意識がある本人の体感的な苦痛を和らげるのに役立ちます。貼るだけなので手軽です。
【水分・塩分補給】〜意識がある場合のみ〜
- OS-1®などの経口補水液(ゼリータイプや水に溶かす粉タイプもあります)
- なぜ良いか?: 緊急時に適切な塩分や水分を補給するために最低一本常備するのがおすすめ。
液体をうまく飲めない状態のためにゼリータイプもあり。
- なぜ良いか?: 緊急時に適切な塩分や水分を補給するために最低一本常備するのがおすすめ。
- 塩分補給タブレット・塩飴
- なぜ良いか?: 意識がはっきりしていて、経口補水液を嫌がる場合などに、水と一緒に摂取してもらう選択肢になります。
【状態を確認する・記録する】〜救急隊に正確な情報を伝える〜
- 体温計(非接触型がベスト)
- なぜ良いか?: 救急車を呼ぶべきか、現場での応急処置を続けるべきかの重要な判断材料になります。非接触型なら素早く衛生的に検温できます。
- パルスオキシメーター
- なぜ良いか?: 指先で血中酸素飽和度と脈拍数を測れます。重症度を客観的に把握し、救急隊に正確な情報を伝えるのに非常に役立ちます。安価なものも多いので、ぜひ備えておきたいアイテムです。
- 緊急連絡先・応急処置マニュアル
- なぜ良いか?: パニック状態でも落ち着いて行動できるよう、【「①救急車を呼ぶ(119)」「②現場責任者の連絡先」「③最寄りの病院」】などを書いたカードをラミネートして入れておきましょう。熱中症の症状レベル別の対応フロー図もあれば完璧です。
【その他】〜万が一の備え〜
- ハサミ(衣類を切断できる救急用が望ましい)
- なぜ良いか?: 体を締め付けるベルトや衣服を素早くゆるめたり、切ったりするために使います。
緊急用バッグのポイント
- 「見える化」が大事: バッグは誰が見ても「熱中症 救急セット」と分かるように、大きく明記しておきましょう。
- 置き場所の周知: 朝礼などで「救急セットはここにあります」と全員に周知しておくことが重要です。
- 定期的な中身のチェック: 使用期限(経口補水液、冷却パックなど)が切れていないか、定期的に確認する担当者を決めましょう。
これらのアイテムを揃えておくことで、「義務だから」というレベルを超えた、本質的な安全管理体制を構築できると思います。
最新ウェアラブル
- ファン付き作業着(いわゆる「空調服®」など): 各メーカー、年々風量がアップするなどアップデートが行われています。2~3年前のモデルを使っている方は、買い替えを検討してみると現行の風量に驚くかもしれません。
- 水冷ベスト、ペルチェデバイスベスト: 近年、ファン付き作業着に続く「着る熱中症対策」が次々と開発されています。
例えば、私たち斫り作業に従事する職人は、粉塵を吸い上げてしまうファン付き作業着を嫌うことがあります。このように、粉塵やニオイを吸い上げて困る現場であれば、水冷ベストやペルチェデバイスのように直接体を冷やすウェアの着用がおすすめです。ご自身の作業環境に最適な一着を選びましょう。 - スマートバンド: 体温アラート機能などを備えたモデルも登場しています。
👉導入は部署や現場単位で。高コストでもリスク低減とモチベーションアップに効果的です。
7. 罰則の仕組みと対応
- 罰則は事業者単位で適用され、現場単位で体制不足の発覚→是正勧告、改善がないと刑罰対象に 。
- 未実施でも処罰対象。記録不備だけでも根拠なく「やっていない」と判断される可能性があります。
8. よくある誤解Q&A
Q1:「うちは元請が対応してくれてるからOK」?
→ ×:協力会社も自社作業員への教育・備品支給義務があります。
Q2:「一人親方は対象外?」
→ ×:労働者を使用すれば事業者責任、人を使わないなら該当しません。
Q3:「水だけで足りる?」
→ ×:汗で失われるのは水分だけではありません。【塩分も同時に補給する】ことが不可欠です。
作業量にもよりますが、水分は1日2〜3Lを目安にしましょう
9.おわりに:仲間と自分を守る「文化」をつくる
今回は、熱中症対策の義務化について解説してきました。
どれだけ立派なマニュアルや高価な装備を整えても、現場に【「ちょっと休ませてくれ」と言えない空気】が流れていては、
何の意味もありません。「顔色が悪いぞ、無理するなよ」と声をかけ合える関係こそが、最強の安全対策です。
この義務化は、ルールだから仕方なくやるのではありません。私たちの現場に、【お互いを気遣い合う「安全文化」】を根付かせるための、絶好のきっかけだと捉えてみてはいかがでしょうか。
この記事が、その一助となれば幸いです。
✅まとめ:斫り・解体屋のための熱中症対策チェックリスト
一つでも「いいえ」があれば、そこが最初の改善点です。明日からできることから、早速取り組んでいきましょう!「文化」の問題でもあります。
最後に、事業者が対応すべき義務のポイントを、我々**「斫り・解体屋」の視点**を加えてチェックリストにしました。自社の体制と見比べてみましょう。
☐ WBGT値の把握: 現場にWBGT計を設置し、毎日記録していますか?
☐ 救護体制の整備: 熱中症発生時の対応フローを決め、全員に周知していますか?
☐ 教育の実施と記録: 熱中症に関する教育を定期的に行い、記録を残していますか?
☐ 休憩所の確保: 日陰やエアコンが効いた涼しい休憩スペースはありますか?
☐ 備品の用意: 経口補水液や冷却グッズをすぐに使える場所に常備していますか?
☐ 【斫り屋POINT】防護具対策: 防塵マスクや保護メガネ着用時の熱対策(こまめな休憩、専用ウェアなど)は考慮されていますか?
👉さらに斫り作業に特化した熱中症対策についてはこちら
【斫り屋の夏】斫り作業特有の熱中症リスクと対策!実践的アプローチ
🌟斫り作業を行うためには、身を守るための適切な保護具の着用が必要です。
こちらの記事にも載せていますので参考にしてみてください。
👉『【はつり作業】気持ちはわかるが、保護具は着用しよう!』